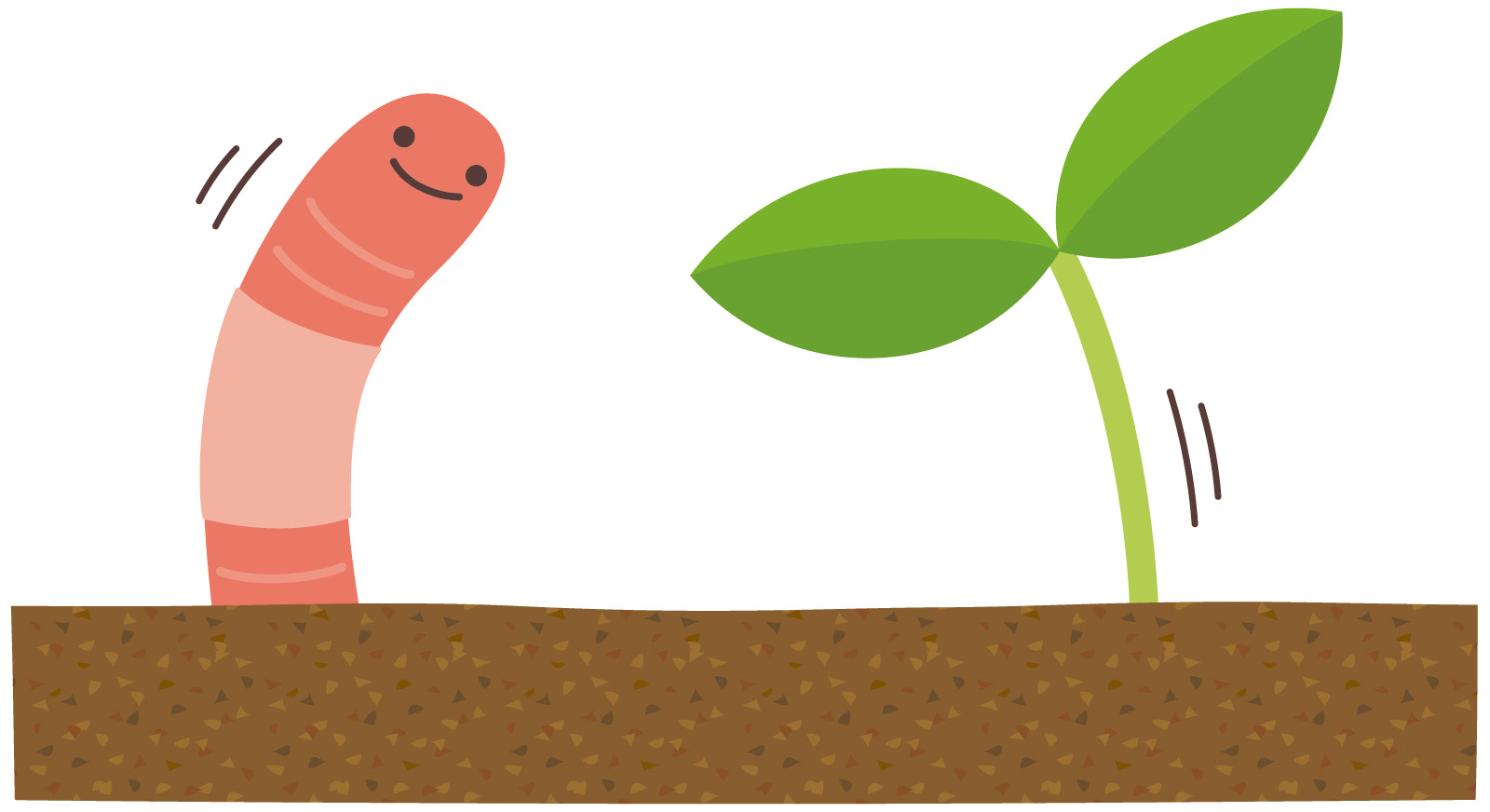このページでは二十四節気「立夏」の七十二候・次候における「蚯蚓出」の意味・由来・読み方についてご紹介しています。
目次
蚯蚓出の読み方
蚯蚓出は「みみずいづる」と読みます。
蚯蚓は「きゅういん」とも読まれますが、これは中国語の読み方です。(発音:qiu yin)
中国で蚯蚓(きゅういん)と呼ばれた理由
1716年に清国の治世に編纂された中国の漢字字典「康煕字典(こうきじてん)」には、次のような意味があると記述されています。
ミミズの身体の特徴として引いたり伸びたりして進みます。この様子は息を吸いこんで吐いたようなようにも見えます。
また、土壌で土をクソほど食べてクソほど糞(クソ)を輩出し、その量は丘が軽く1つできるほどになる例えられたことから、その様相をイメージした言葉が「蚯蚓(きゅういん)」になるようです。クソクソクソクソ
蚯蚓出とは?
蚯蚓出とは、二十四節気の「立夏(りっか)」をさらに3つの節気に分けた「七十二候」の1節です。
72の節気を持つ七十二候においては「第二十侯(第20番目)」の節気、「次候(じこう)」にあてられた語句になります。
太陽の黄経は50度を過ぎた地点です。
立夏期間中のその他の七十二候の種類・一覧
初侯:蛙始鳴
- 関連記事:
 蛙始鳴の意味・由来・読み方
蛙始鳴の意味・由来・読み方
次侯:蚯蚓出
末侯:竹笋生
- 関連記事:
 竹笋生の意味・由来・読み方
竹笋生の意味・由来・読み方
蚯蚓出の意味・由来
日本(略本暦)での解釈
「蚯蚓出」とは、「ミミズが地上に這い出てくる頃」という意味があります。
端的に訳せば「冬眠していたミミズが地上に這い出てくる頃」となります。
ミミズは土壌に生息する生物ですが、日差しが強くなり地中の温度が上昇してくると地上へ這い出てきます。つまり、そろそろ日差しが強くなってくる初夏の始まりを「ミミズが這い出てくる時期」と言い換えた言葉です。
ちなみに「ミミズ」という言葉の由来は、目のない生物であることから「目が見えず」という言葉が転じて「メメズ」になって→「ミミズ」で最終的に着地したとされる説があります。
ミミズは土壌改良に一役買っている
なんと!知らなかった方も多いと思われますが、ミミズは農家にとっては益虫であり、お金を出して買ってまでしてワザと田畑に棲ませていると聞けば驚かれますでしょうか。
ミミズに目がないのは土をひたすら食べるだけで生きていけるからです。厳密には土の成分にも含まれる有機物や微生物を食べているのですが、これらをシコタマ体内にブチ込むことによって、いずれ糞(クソ)を垂らします。
ミミズの糞(クソ)も、やはり固形状になり、ミミズの排泄する糞(クソ)が多くなればれなるほど排水性と保水性を兼ね備えた土壌ができあがります。(これを専門用語で「団粒構造」という)
その上、ミミズの糞(クソ)の成分は窒素や炭素を多く包有し、農作物の栄養分として吸収されやすいカルシウム、マグネシウム、カリ、リン酸などの成分も豊富に含まれています。
すなわち、作物を育てるのに適した土壌ができあがるワケです。農家が積極的にミミズを田畑に用いるのにはこのような背景があったからなのですね。ウフ
中国(宣明暦)の立夏の次候・第二十侯の七十二候は「蚯蚓出」!
中国における立夏の次候・第二十侯の七十二候も日本の七十二候と同じで「蚯蚓出」になります。
蚯蚓出の意味
意味合いは「蚯蚓が地上に這出る頃」です。
中国の一部の村では雨が降った後の湿った土中に向けて、電気ショックを用いてミミズを大量捕獲して他国へ販売していたようです。
しかし、その副作用として土壌の状態が悪化し、作物が育たなくなったという事例があったようです。
この話は、ミミズが農家にとってどれほど重要な位置付けの生き物なのかが分かると共に、ミミズと共存していくことの重大さが身に染みて分かります。
蚯蚓結は蚯蚓出とセット!
二十四節気の「冬至(とうじ)」の七十二候「第六十四侯(第64番目)」の節気、「初候(しょこう)」に集録される「蚯蚓結(12月22日〜26日頃)」と蚯蚓出はセットです。
蚯蚓出で「蚯蚓が地上に這出る頃」とし、蚯蚓結で「蚯蚓が土中で動かなくなる頃=冬眠する頃」と蚯蚓の動き方を参照して1年の移ろいを解釈しています。
蚯蚓出の日にち(期間)
- 太陽暦:5月11日〜15日頃
- 旧暦:四月節(四月の正節)